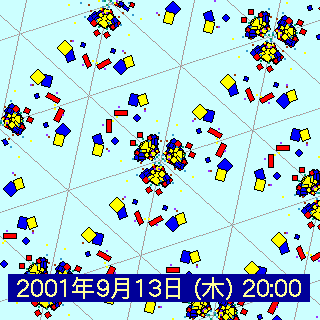 ネタ切れになると始まる「私の電脳歴」シリーズです。前回のPalmな時代1から実に四ヶ月も経過してしまいました。まぁ、つながりも何もないので良いのですが、、、
ネタ切れになると始まる「私の電脳歴」シリーズです。前回のPalmな時代1から実に四ヶ月も経過してしまいました。まぁ、つながりも何もないので良いのですが、、、
Palmのシンプルな使い良さに感銘していた私は続々と発表されるPalmデバイスに物欲を刺激され続けていました。しかしVisor Deluxeはすこぶる順調で新しいデバイスを購入する理由を自分自身で見つけられません(今だと、「欲しい」というのが理由になるのですが)。そんな時、2000年にPalmデバイスの販売に参入したソニーから2001年にハイレゾ(320×320)のCLIE PEG-N700Cが発表になりました。これには大いに興味がわきました。色々と情報を調べてみるとソニーのプログラムコンテストに応募宣言をするとN700Cがもらえる(最初は貸与で、ちゃんとコンテストに出品して初めて自分の物になる)とのことです。
斯くして 第2回「クリエ」プログラムコンテストの「応募宣言します!」に企画を提出したところ見事に採用されてしまいました(たしか10作品ほどだったと思います)。Palmプログラミングの準備はしていたものの、まだ一つもプログラムを書いたことが無かったので、今にして思えば無茶な話です。しかも、万華鏡シュミレーター(かれいどすこーぷという名前です)という、いかにも企画を通すための思いつき(実際は、随分前からPalmとは限らず何かしらの形で作ってみたかったのですが)のような実現できるかどうかも定かでない題目です。
プログラムを始めてから、おお浮動小数点や三角関数って無いんだ(math.libというのが入っていれば使えます)、なんて気づく始末です。物を回転させるのに三角関数は欠かせません、仕方なくテーブルを引く形で三角関数を導出し、全てを固定小数点で計算しました。実際には、この方法を使ったことにより何とか満足のいく速度で図形を動かすことが出来たのだと思います。
3ヶ月ほど悪戦苦闘の末、何とかコンテストに出品し、N700Cは自分のものとなりました。残念ながらコンテストで入選には至りませんでしたが、ベクターさんやMuchy.comで、こんな役に立たないPalmwareは珍しいとレビュー記事を書いていただきました。
その後、入手したCLIE SJ33が私の最後のPalmデバイスとなりました。ということでPalm OS5を知らないままに私のPalm時代は終わりを告げたのでした。
一台のザウルスを表面のつや消し塗装がすり減るまで使った後に手にしたのはIBM WorkPad c3 40Jでした。Palm VのIBM版で黒い筐体がThinkPadとおそろいの美しいデバイスです。ただメモリーが2MBとおそろしく小さいため追加のソフトなどを導入すると直ぐにパンクしてしまいます。そこで既にネット上で公開されていた情報を頼りにメモリーの張り替えを行いました。8MBに増設されたメモリーのおかげて追加のソフトを色々試すことが出来、いろいろな意味で楽しむことが出来たデバイスでした。
その後、Visor Deluxeを購入(たしかWorkPadが壊れてしまったのだと思います)。WorkPadに入力していたデータは常に複数のパソコンに同期させていましたので、簡単にVisorにも移すことが出来ました。WorkPadを使用し始めたときから、ハードリセットしても直ぐに再現できるデータに感心していましたが、機種が変わってもデータが簡単に引き継げることに改めて感激しました。
パームウェアの作成にも興味は持ってました。しかし数多くのパームウェアが公開されていたため必要性がありませんでした。それが思わぬことから、後にパームウェアを作ることになります。それについては日を改めて書くこととします。
PS. ここ数日、サーバーが不調でブログにアクセスすることが困難でした(連絡してるのだけどなぁ)。今日はどうかな?
実に一年振りとなる「私の電脳歴」カテゴリーのエントリーです。ネタ切れの時に昔を懐かしんで書いていたカテゴリーです。あまりに昔の事で時系列になっているかどうかも怪しいです。 🙂
小さな機械が好きでポケコン使ったり電子手帳に入れ込んだりしていましたが、今にして思い返すとOMRON Massifを購入した時点でモバイラーになったと言えるのかもしれません。
Read the rest of this entry
ほとんど何時のことかも覚えていないし型番も不明なくらい昔のことです。
シャープがビジネスマン向けに電子手帳を発売したときは、とてもあこがれました。会社からもらう紙の手帳を使っていましたが非効率さが気になって、当時流行のシステム手帳なども試して見ました。リフィルとか揃えたり、パソコンでシステム手帳向けの印刷物作るのは楽しかったですが、なかなかうまく使いこなせなかったです。固定的な情報には向いているのですが、ダイナミックな内容には向いてない感じがしました。そんなこともあり電子手帳には大きな可能性を感じていました。
しばらくして、筐体が灰色のプラスチック製に変わった廉価品が出てきたので購入しました。独特のローマ字入力と小さな液晶画面をうまく使った効率の良いユーザーインターフェースが構築されていました。追加のアプリケーションがICカードで供給されていて私は常時、国語辞典を入れていました(昔から漢字に弱くて^^;)。このICカードも本体の透明なタッチパネルの下に挿入されカードの表面の印刷が操作パネルとして機能するという秀逸なものでした。本当に感激するほど良く出来たもので、筐体の表面が磨り減るまで使いました。
その、使い勝手の良さは同じシャープのザウルスにも引き継がれて行きました。ザウルスも、ちょっとお手ごろ価格になってから購入しました。実際に使うまでちょっと疑っていたのですが、手書きで漢字が実用的に入力できるのに驚きました。これも一台を磨り減るで使い込みました。
こうして来るべきPDA時代にどっぷりつかる下地が出来上がって行くのしでした。
昔々の事です。日本のPC市場を事実上支配していたNECの9801にも黒船がやってきました。IBMのDOS/VとAT互換機です。IBMはすでに5550という独自企画の日本語DOS搭載機をビジネス用として販売していました。個人ユーザー向けの機種もありましたが、やはり裾野を広げるには至りませんでした。そこに登場したのがDOS/Vです。これはIBM PC-AT互換機、当時の認識では英語版のPC、にフロッピーディスクを入れてブートすれば日本語の使えるパソコンになってしまうというものでした。
日本でも外国人とごく一部のマニアなかたがたがAT互換機で遊ばれていたので、それを扱うお店もいくらかはありました。最初の頃はAT互換機もかなり高価でしたが、ハードを自由に選べるのは魅力的でした。
私が最初に購入したのはNBCCと言う会社が販売していた20GB HDD内蔵のA4ノートでした。キーボードも英語仕様の海外向けの製品です。DOS/Vを立ち上げて漢字が表示されたときは感激しました。CPUは後からCyrixのものに自分で張り替えたような気がするので386SXだったのでしょう。その次はショップブランドの386DX33ミドルタワーケース。その先は現在にいたるパーツばら買い時代突入です。
性能こそ当時とは比べものにならない現在のPCですが、今でもDOS/Vのフロッピーを入れればブート出来るはずです(HDDを使うのは難しいです)。移り変わりの早い世界において、これだけ息が長いスペックというのは大したものでしょう。
次世代のハードはROM BIOSの呪縛から解き放されると聞いています。インテルMACがそれを先取りしていることからもAT互換機時代の終焉も近いのでしょう。
日本のパソコン史を語る上で避けて通れないのが NEC PC-9801 シリーズです。私は 98 に対して思い入れが強いわけではありませんが、それでも3機種ほど購入しています。記憶はやや曖昧ですが PC-9801VM2, PC-9801VX2, PC-9801RA21 と 80 年代半ばから 4-5 年にわたって買いつづけたように思います。買い替えのたびに前の機種を中古店に売りに行ってました。値段は今のパソコンよりかなり高く (収入は今よりかなり低いし) 苦労して買っていたのだと思います。PC-9801 には ROM BASIC が搭載されていましたが、もっぱら MS-DOS を使っていました。初期のころは、まだ MS-DOS が完全に世の中を支配していたわけではなくて NEC は CP/M-86 なども販売していました。
このころパソコンで何をやっていたか、はっきりとした記憶があまり無いです。パソコン通信の黎明期でもあり、いくつかのプロバイダーのテストが始まっていました。最初はモデムではなくてアコースティックカプラーという電話の受話器を通して通信する方式で始めました。通信プログラムも特に標準的なものは無くてパソコンに備わっていたターミナルモードの使い方とかがプロバイダーのガイドブックに書いてありました。私は BASIC で簡単な通信プログラムを書いて使っていました。ログが取れることが唯一の特徴という簡単な物でしたが当時としては十分でした。
もう一つは、やはりプログラミングです。当時の NEC MS-DOS には MASM 3.0 というマクロアセンブラーが付属していて、それで何やらプログラムを書いていました。何を作っていたかは、ほとんど覚えていません。ひとつだけ記憶にあるのは GAME86 Shell というプログラムを月刊アスキーに投稿して、(忘れたころの) 1988 年 9 月号に掲載されたことです。GAME 言語というのは 8 ビットプロセッサー時代の VTL ですが、それを MS-DOS の上で Shell 言語として作り直した物でした。原稿料という物を初めてもらった良い思いでです。
おそらくは 1980 年代の初めから中ごろにかけての事だったと思います。カシオのプログラマブル電卓とシャープのポケコンで遊んでいた時期がありました。どちらも、結構高価なものでしたが店頭で遊んでいて気が付くと購入して帰途についているという感じでした。もともと小さな機械好きの種を持っていたのでしょうが、このころ見事に発芽したといえるでしょう。
カシオのプログラマブル電卓はインターネットで探しても、それらしいものが見つからないので型番とかは分かりませんが、今でも動作可能な状態で日本の自宅に置いてあります。現在の関数電卓などとくらべるとかなり大きくて緑色でぎらぎらと光るディスプレイを持っています。ただし 8 セグメントの表示なので表現できるのは数字と意味不明の記号のみです。それを使った簡単な条件分岐やジャンプ命令を駆使し小さなプログラムを組みます。作ったプログラムの保管もできないしステップ数というか入力できる文字数が少ないのでできることに限界はあります。
シャープのポケコンは確か二つ買いました。どちらも PC-12xx で、後から買ったのは多分 PC-1261 だったと思います。CE-125S というドッキングステーションのような物も買い足して、自慢の一品でした。小さいながら2桁の表示ができ、そこそこ大きなプログラムを組めるメモリー(といっても10K くらいかな)が載っていました。出かけるときにも持っていけるプログラム環境というのが何ともうれしかったです。この機種で可能であったかどうか覚えてはいませんが BASIC に PEEK/POKE というメモリーを直接操作する命令と CALL という機械語のルーチンを呼び出す命令を使い機械語で楽しんでいる人たちも世の中には居ました。わたしはひたすら BASIC を使っていました。
TK-80BS の次に購入したのは Z80 で 64KB RAM 搭載の MZ-80B でした。ディスプレーとカセットテープによる外部記憶が一体になった銀色の筐体で当時としてはカッコの良いコンピューターでした。特にマニアに受けていたのは回路図やモニターのソースコードが付いていた点だったかもしれません。最初高かったフロッピードライブも途中から入手しやすくなって、最終的にはフロッピードライブ、プリンターと買い揃え贅沢な環境を整えていました。
インターフェース誌に2パス・アセンブラのソースコードが載っていました。他の機種(ソースを見て何の機種かピンときたのですが忘れてしまいました)をターゲットにした物だったので変更の必要な場所をハンドアセンブルでパッチしながら移植しました。まわりの数少ない MZ-80B のユーザーの中にアセンブラに興味を示す人がいなかったので独りで使っていました。今にして思えばインターフェース誌にパッチとして投稿すれば良かったと思います。
プログラムテープをバックアップコピーする手段とかは無かったのですが公開されているモニターのソースとアセンブラのおかげで、まるまるコピーするプログラムを作ったりしていましたが、今と違って公開の場がなかったので、これも自分専用プログラムでした。
フロッピー・ドライブのドライバーのソースまでは公開されていなかったのですが、逆アセンブル(ツールを持っていたのか自分で作ったのか忘れました)して解析していました。当時も中国に出張ベースで来ていて、空港行く直前に思いついてリストを印刷し一ヶ月の出張期間中の暇つぶしに解析をしたものでした。確かリードでエラーすると何回かリトライするコードが入っていて感心した記憶があります。そのおかげてフロッピーも自分のプログラムから直接扱うことができるようになりました。自由自在に楽しめた良いマシンでした。MZ-80B で遊んでいるうちに世の中は 16 ビット・コンピューターの時代に変わっていましたが、ずいぶんとお金がかかるので直ぐにはついて行けなかったです。
何年の事だったか忘れましたが、前に書いた TK-80 が日本で流行っていたころではないかと思います。名古屋で開かれていたエレクトにクスショーを見学に行ったときのことです。ここで期せずして APPLE II に出会いました。APPLE II については有名なので改めて紹介する必要もないと思います。
そのスマートさはもとより、そこで動いていたスタートレックにあこがれました。結局 APPLE II を所有することはありませんでしたが、その後、色々なバリエーションのスタートレックで遊びました。単純ですし、難しいゲームではありませんが、いまだ何か特別なゲームとして心に残っています。
日本でワンボード・コンピューターに熱中している人たちがいる一方で海の向こうでは、こんなにもスマートなコンピューターが動いているということを思い返してみると、なんともすごいことであると再認識しています。すぐに日本でも MZ-80 や PC-8001 が出てきて形の上ではすぐに追いついてくるのですが、何かもっと文化的な要素において遅れを取っていたような気がします。
会社に入って仕事でコンピューターに囲まれる生活を始めましたが個人的にコンピューターを所有するのにはだいぶ時間がかかりました。入社当時すでにワンボード・コンピューターというものが存在していました。Intel 8080 という 8 ビットマイクロプロセッサの互換チップの搭載された NEC の TK-80 は憧れの的でしたが新入社員に手の出る金額ではなかったです。
何年かして、やや廉価版の TK-80E が出てから、それと TK-80BS という BASIC 言語搭載のアドオン・ボードを同時に購入しました。かなりの覚悟の購入だったと思います。
キーボードは TK-80BS に付属していて表示は家のテレビを使用します。ちょうど使わなくなった 14 インチの白黒テレビがあったので、それが TK-80BS 専用になっていました。自分の作ったプログラムの保管には普通のオーディオ・カセットを接続して行います。データーをプログラムで変調してピーギャーという音に変換して記録していました。TK-80BS が使っていたかどうか覚えていませんがカンサスシティ・スタンダードという有名なプロトコル (変調方式?) がありました。ベーシックも使いましたがハンド・アセンブルによるプログラミングで基本的な事柄を試してみる方が面白くかったと記憶しています。
最初から用意されている周辺機器はテレビとカセットテープだけでしたが搭載されているペリフェラル・インターフェース 8255 のポートの1つ半 (8255 知っている人居ます?) は空いていて自分で好きなように使用できました。型番は忘れてしまいましたが 40 桁の EPSON 製のドット・プリンター、おそらくは単体で売るものではないのではない、をある程度の安値で購入することが出来たので、それを接続して使用していました。TK-80E 上の空いているランドに自分で小さなコネクターとプルアップ抵抗を半田付けして接続しました。プリンターを動かすためのプログラムも自分で機械語で作成します。その為に 8255 のスペックシートを BIT-INN で購入した記憶があります。TK-80BS のベーシックには最初からプリンター関係のコマンドが用意されていて、ある決められたアドレスに自分でプログラムを書き込んでおくとベーシックからプリンターが使用できるという、ありがたい仕掛けが成されていました。おかげで最低限の努力でプリンターを使いこなす環境が出来上がりました。
高校時代に作った FORTRAN の万年カレンダーを移植してプリンターにカレンダーが打ち出された時の達成感、感動は忘れられません。実験ばかりではなく、カセットテープの曲名ラベルを作成するプログラムなどを作って半実用的な使い方もしていました。
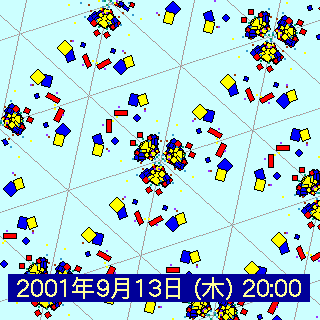 ネタ切れになると始まる「私の電脳歴」シリーズです。前回のPalmな時代1から実に四ヶ月も経過してしまいました。まぁ、つながりも何もないので良いのですが、、、
ネタ切れになると始まる「私の電脳歴」シリーズです。前回のPalmな時代1から実に四ヶ月も経過してしまいました。まぁ、つながりも何もないので良いのですが、、、